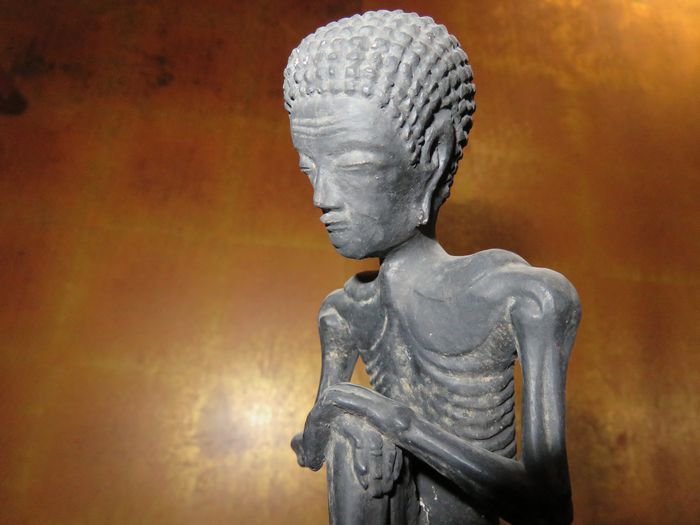
|
「 |
住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。
「あけまして おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。」称名
今月は「
「信心をいただく 足下から道が開かれる」菅原 信隆 樹心社 に次のように書かれている。
『自分を振り返る眼がなければ気が付きにくいが、我々が日常こころ安らかに生活している時には、何かを信じているのである。
それが家族であったり、友人であったり、会社や物、金といったぐあいに人により時と所によってもこれは違うが、何かを信じている。
信じておれるからこそ心が穏やかなのである。
したがってその信じる心が崩れて行く時には、その穏やかさも崩れざるをえない。
私が大学生の時のことである。間借りしていた学生アパートの大家さんの所に、近くの奥さんがよく遊びに来ていた。
両方とも小学生の子供を二人持ち、遊びに来る奥さんの方は二人とも女の子であった。しかし、どうしても男の子がほしかったようである。
そこで三人目を持つことにしたのであろう。お腹の中に新たな生命が宿った。願いがかない、生まれてきたのは待望の男の子である。
首がすわるようになると、その子を抱っこしてしょっちゅう大家の所に遊びに来るようになった。
扱い方を見て、母親の子供をかわいく思う気持ちが手に取るようにこちらに伝わってきた。
しかし、結婚もせず勿論子供もいない大学生のこちらから見ていても、こんなに甘やかしていいのかと思うくらいに、ほとんど我慢をさせるということがないのである。
泣けばすぐおっぱいをあげる、あやす、といった具合である。こちらは子育ての経験が無いし他人の子供であるからだまって見ているだけであったが、心配になるくらいの甘やかしようであった。

間もなくこちらは卒業をし、その家を後にしたが、それから十五年くらい経った頃であったろう。懐かしくなって大学を訪れ、挨拶を交わして少し世間話をしてから おもむろに尋ねてみた。
「あそこの男の子は今どうしていますか?」と。すると奥さんの顔が急に曇ったようになり、あまり言いたくなさそうな口ぶりに変わったが答えてくれた。
「実はねえ、あまり大きな声では言えないんだけど、親があまりに甘やかしすぎてねえ、それで子供がぐれてしまってさあ、今は何処へ行ったかわからないの。 親はそこにまだいるけど話をすることも無くなってねえ、付き合いがてんで無いの」と。
数えれば男の子は高校一年生前後である。その子供がぐれてしまって、何処へ行ってしまったのかわからなくなっているというのである。
「やっぱりなあ」とは、その時の私の思いであった。
親が子供を甘やかすということは、子供の思いのとおりに許すということである。
そんな育て方を小さい時よりされ続けたなら、子供は自分の思いどおりに世の中とはなるもんだと思ってしまうであろう。
そのように世の中が「見える」のである。「見える」とは「信じる」ということである。
大きくなればなるほど世の中は自分の思いどおりには行かなくなる。それが見えてきた時に、その子供は自分の信じていたことが崩れて行ったのであろう。
それがぐれることにつながったように思われた。
人がそして世の中がきちっと見えるということは、きわめて大切なことである。それができた人の中には、大混乱の中にも道を切り開き、大きく成功を遂げることのできた人がいた。
戦国時代に生まれた信長、秀吉、家康の時代に活躍した武将の一人に、

家康には厚遇され、家康亡き後には秀忠、家光にも頼りにされ、最終的には三十二万石を与えられて伊賀、伊勢を領有する大大名となった。
しかし出自となると大したものではない。高虎が最初に
それからというもの、織田信澄、豊臣秀長、豊臣秀保、豊臣秀吉と続き、最後が徳川家康であった。八人の主君に仕えたのである。高虎の世渡りの上手なことがうかがえよう。
「忠臣は二君に仕えず」というのが武士道であるように思う人がいるかもしれぬが、この哲学が広まったのは江戸時代であり、戦いの世の中では高虎のような生き方というのは当たり前のことであった。
忠誠を誓った主君がダメとわかれば、簡単に離反し裏切ったのである。信長は信頼しきっていた明智光秀に裏切られ、関ヶ原の戦いでは裏切りが裏切りを呼んで東軍の勝利に帰した。
したがって戦いの世の中では、いかに人を見抜くかが極めて大きな力となったのである。
信用できぬ部下を持つと自分の首が危ないのであり、間違った主君に従うと自分だけでなく、一族郎党が命を奪われる危険性の有ったのが戦国の世の中であった。
したがってその時代には、「人間とは心の底から信じることができる存在ではない」と信じる人が多かったということになるであろう。
人をいかに見抜くかは、現今でも大切なことである。人だけではない。物事をいかに見抜くかということも同じである。
見方が間違えば、自分の人生そのものを狂わせかねない。
人間がそしてその住む世の中がいったいどんな姿をしているのか、その本当のところが見えることは、我々が生きて行く上で大きな力となる。
「見える」とは、そのまま「信じる」ことである。人間は今まで何をどう「信じ」て来たのか。この問いは未来に向けても同じように発していいであろう。
この書はそれを尋ねたものである。己のあるべき姿を考える一助としていただければ、幸甚この上もない。』
【「信心をいただく 足下から道が開かれる」菅原 信隆 樹心社 より】

このように序文に書いてあります。
人間をどのように育てていくことが大事なのか?何でも自分の思い通りになるように育てられた人間が、如何にわがままになり、自己中心的な人間になっていくか!
他人だけでなく、自分自身の課題として、大いに考えさせられる文章であります。
また、この厳しい世の中で、生き残るためには、どのように生きて行けばいいのか?そんなことも考えさせられます。
ただただ真面目に生きていれば道が開けるというものではないのでしょうか?
そんな疑問符も投げかけられているように感じます。
こんな世の中だからこそ、逆に、「阿弥陀さまは、今、見てござる」という法語のように、自分を超えた世界を感じ、尊び、敬う生活というものも、大切なものだと思わずにおれません。
一生懸命頑張って努力していけば、ご褒美をいただけることもあるのではないか?そんな甘い事も考えたりします。
他人の眼を意識していることで、相当な労力を奪われ、疲れ果ててしまうことも多い気もします。
他人よりも、一人でいても、仏さまは、いつも、「見てござる 護ってござる 」という、自分を超えた世界に目覚めさせられていく道を学ぶことが大事であり、厳しい娑婆の中にあって、 人間に求められているものなのかも知れません。
私に、三歳の男の子の孫がいます。先日、ミニカーを走らせるハイウエイの付いたオモチャを買ってやりました。
組み立てて、電池を入れて、スイッチを入れると、凄いスピードで、車が走り出す、というオモチャでした。
「凄いスピードだねー。ちょっと速過ぎるのではないか?」と私が言うと、息子が「高速道路だからね!」と言いました。
なるほど高速道路という設定だから、速くてもいいわけですね。
そばで見ていた、92歳の私の母が、「ストップ!ストップ!ストップはどうしたの?」と言いました。
スイッチを消さない限り、ミニカーは止まりません。極端に言えばスイッチをきらなければ、電池が切れるまでずっと走り続けていくことでしょう。
私は、「ストップ!」という母の言葉を聞きながら、ふと、自分自身のことを振り返りました。
私の今までの仏法聴聞と、重ね合わせて考えさせられました。
朝から晩まで、「止まること」無く、ずっと走り続けて来た、今も此の瞬間も、止まることなく、走り続けているのではないだろうか?
昔、法話で聞いた法語「親に抱かれて、親探し、くたびれ果てて 親のふところ」という法語を思い出したのでした。
阿弥陀さま【親】に抱かれながら、「阿弥陀さま【親】は、何処に居るのか?」と走り回っていたのではなかっただろうか?

こんな法語がありました。
「そらごとと思いし浄土がまことにて、
まことと思いし娑婆が そらごと
み仏は いまだ見えざり
聞くたびに
いづくにおわすと空を たずぬる
み仏は いづくに おわすと聞きぬけば
求める前に抱かれてあり」
この法語が有難く響いてきます。
浄土真宗の大事な言葉に 「
先日、私より一歳年上の方の四十九日、納骨法要に参りました。
墓に「摂取不捨」【せっしゅふしゃ】という言葉が刻まれてありました。亡き主人が希望した言葉だと奥さんから聞かされました。
この言葉を子孫にも大事にしてほしいと願われたのでしょうか?
奥さんも、この「摂取不捨」という言葉を色々調べられたそうです。
「私たちはもうすでに摂取不捨【せっしゅふしゃ】と、仏さまに救われているのです。」と言われました。
本当に、私自身が育てられるご縁でした。
十方微塵世界の 念仏の衆生をみそなはし 摂取してすてざれば 阿弥陀となづけたてまつる【「和讃」親鸞聖人】
「数限りない すべての世界の念仏するものを見通され、
摂め取って決してお捨てにならないので、阿弥陀と申しあげる」 とほめたたえられています。
『阿弥陀経』には、「光明無量」「寿命無量」だから阿弥陀と名づけると書かれています。
「摂取不捨」こそは阿弥陀さまならではの特別な願いだからです。
「摂取不捨」とは、「仏さまに背を向けて逃げ続けているものを 追いかけ続けて下さる」働きという意味です。

この「摂取不捨」について、この和讃には「左訓」【さくん】といって、語句の左側に小さな文字で、意味や訓読みなどを記されている部分があります。
そこでは重要な意義を、示しておられます。
「ものの逃ぐるを追はへとる」と、左訓【さくん】に書いてあります。
「阿弥陀仏」という仏様は、「逃げる者を追いかけ続けて下さる仏様」だということです。
阿弥陀様は「自分の方を向いた者だけ救う」という仏様ではありません。
私たちが、仏さまと真反対の方向を向いていようとも、【煩悩とは、仏様と反対の方向を向いているもの】
たとえ仏様に背を向けて逃げ続けていたとしても、追いかけ続けて下さる仏様なのです。
もう一つ、左訓【さくん】には「ひとたびとりて永く【ながく】捨てぬなり」ともご教示下さっています。
「お念仏一つで、どうして悟りを開くことが出来るだろう?」そんな都合の良いことが本当にあるのだろうか?
そんな疑問がわいてきてもおかしくはありません。
問いを持つことは大事なことですね。
先日、ある家にお参りに行き、いつものように「阿弥陀経」を拝読しました。
その家の奥さんは、後ろでいつも、一緒に、「阿弥陀経」を読まれています。
ある時、おおよそ、次のような質問をされ、驚きました。80歳くらいの方です。
「私は、阿弥陀経を読んでも、意味が分かりません。意味が分かって救われるのですか?」と聞かれました。
「最近実兄も亡くなった。自分も80歳を超えて、いつどのようなことになるか知れない。しかし、阿弥陀経を読んでも、意味は分からないし、どうしたら本当に救われるのでしょうか?」
そういう生々しい、自分自身の中から湧き出て来たような問いかけでした。
私は「わかったら救われるという事ではなく、阿弥陀さまの働きによって救われるのではないでしょうか?」とやっとの思いで答えました。
こんな問いかけに、正面から向き合い、ちゃんと答えられなくては、坊さんの値打ちはない。
また、反面、この奥さんの問いかけによって、私自身が問われていると同時に、私自身が育てられている、私の方が教えられているのではないか?
そんな気もするのです。
今度会う時に、「摂取不捨」【せっしゅふしゃ】についての話が出来ればいいのではないか?
「摂取不捨」とは、「ひとたび仏さまの御手【みて】に抱かれた者は、必ず仏に成らせていただくのです。」という意味です。
死別は悲しく辛いものですが、その姿を通して、身をもって、私に教えて下さっている。
私は、「教える」のではなく、色々なご縁によって「教えられている」「育てられている」のではないのか?
私たち真宗の信徒が歩む仏道とは、念仏申しながら歩むことだと教えられました。
「南無阿弥陀仏」とお念仏申す身に成らせていただいたことは、すでに阿弥陀様の御手に抱かれた証しです。
だから、共に浄土で会えるのです。

私達は、いつ、どんな状態で、阿弥陀様のことを忘れてしまうかわかりません。
しかし阿弥陀様の方は、ずっと、私たちのことを決して忘れません。
源信和尚のお言葉に、「大悲無倦」【だいひむけん】という言葉がございます。
「われまたかの摂取の中にありといえども、私は、煩悩にまなこさえらている。」
「煩悩のまなこにて仏をみたてまつることあたわずといえども」
「大悲無倦」です。つまり、「大慈大悲の御めぐみものうきことましまさず。」ということです。
「常に照したまうという。無碍の光明、信心の人を常に照らしたまうという意味です。」
「常に照らす」というは、「常に護りたまう」という意味です。
「我身を、阿弥陀様は、大悲ものうきことなくして、常に護りたまうと思えとなり。」という意味です。
「摂取不捨のこころ」「念仏衆生 摂取不捨」のこころを表しています。
「摂取不捨の仏様」ですから。「摂取不捨」は、簡単な言葉ですが、その中には大きく深い、阿弥陀様ならではの特別な願いが表されている言葉です。
ある信者のお婆さんは、生前、 「
「
南無阿弥陀仏
『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』
☆☆法語☆☆
| *花は嘆かず |
| わたしは |
| 今を生きる姿を |
| 花に見る |
| 花の命は短くて |
| など嘆かず |
| 今を生きる |
| 花の姿を |
| 賛美する |
| ああ |
| 咲くもよし |
| 散るもよし |
| 花は嘆かず |
| 今を生きる |
| 【坂村真民】 |
ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌
最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。
「今ここでの救い」

