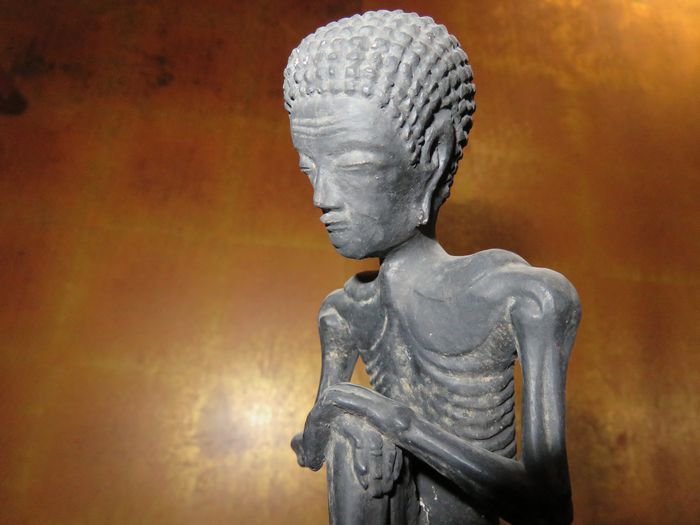
|
「お |
住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。
今月は「お
「本願寺新報」【1999年4月1日】に、「お仏壇と私」(31)に次のように書かれています。紹介させて頂きます。
『仏は遠い存在だけでなく そのまま近い存在である
これは、三月の法語カレンダーの言葉です。毎朝お仏壇の扉を開き、灯火をつけ香をたき、お仏飯を供え、聖典を拝読し、心の安らぎと気のひきしまるのをおぼえますが、 この法語にハッとさせられました。
若かりしころ、こんな疑問をもってお寺を訪ねたことがあります。
「先生、なぜ人間に生まれて来たのでしょう。人間はどこから来てどこへゆくのですか」
ところが先生は答えるどころか手を叩いて大きな声で、「あっ、めでたい、めでたい。良い問題を持ったね。一生涯問い続けなさい」と。
またある時、「あんたは大きなものにいだかれて生きているんだよ。自然を拝んだことがあるのか・・・。
あんたはとらえよう、とらえようとするが、とらえんとするは とらえぬなりだよ。姿、形あるときは仏とは申さず候・・」と、目に見えぬ仏の心にかようこと、仏の願い、 真実の親の心ばえを聞かせて頂くことが大切だと教えて下さいました。
また、ある時は、「如来所以興出世 唯説弥陀本願海 弥陀の本願を聞かせていただき、やがて無量寿・無量光明の仏にさせていただける身とは、何と有難いことか」と、 聴聞をすすめた父親のことを思い出しました。
浄土真宗の教えを心の依りどころとして、代々お念仏を相続し、二百有余年を経たわが家のお仏壇。
聖典は先祖の信心の生活の深さを伝えるごとく、紙面の隅はかげろうの羽根のようにすきとおり、文字は読みとることができないところもあります。
でも代々が求め続けられたことに思いを馳せる時、仏は遠い存在だけでなく、今、私の上にはたらき、南無阿弥陀仏のお念仏によびさまされ、近い存在であると気付かされました。
中田久美子【富山県】 』
「仏は遠い存在だけでなく そのまま近い存在である」「今、私の上にはたらき、南無阿弥陀仏のお念仏によびさまされ、近い存在であると気付かされました。」
と言われています。
お仏壇というと、何か陰気なもの?ついつい自分とは関係ないものだと、仏様も自分とは無関係なものだという気持ちの人が多いのではないでしょうか?
この人は、先祖を偲びつつ、先祖が求め、心の依りどころとした、浄土真宗の教え、というものに、思いをめぐらせ、今の私の上にはたらく、南無阿弥陀仏のお念仏と味わっておられます。
今の私の上にはたらいているお念仏のはたらきに目覚めること、それを「信心」というのでありましょう。
「本願寺新報」1998年12月1日、「お仏壇と私」(28)に次のように書かれています。

『「蓮如上人仰せられ候。本尊は掛けやぶれ、聖教はよみやぶれと、対句に仰せられ候」のお言葉通りのお品を大切に相続させていただいております。
ご本尊には、准如上人花押、お脇掛けの親鸞聖人は、お台座(礼盤)の上にご影ではなく、「親鸞聖人」の文字、そして右下に「大谷本願寺」、左下に「釋准如」との花押がございます。
蓮如上人のお脇掛けは、ただ黒々と古びて何も見分けがつきません。
両親の古里・富山から北海道の小樽、北見と四百年近くわが家のお仏壇に掛け続けられた、古色溢れる尊いお姿です。
また、読み続けられた「正信念仏偈」「浄土和讃」「高僧和讃」「正像末和讃」、そして大きな厚い「御文章」の巻末には、「釋寂如」との花押が記されています。
この尊いお掛け軸を朝夕仰ぎ、お聖教を声高らかに拝読し、「いさみのお念仏」をお称えしたでありましょうご先祖のお姿を偲びながら、私も、いつの間にか手ずれのした大きな「御文章」を 開き「夫れ秋モサリ春モサリテ・・」の章を読ませていただきました。
以前、主人の両親が北見へおいでの時のこと、おみやげは、ご法話の本でした。
それを仏前にお供えし、お念仏申していた父の後ろ姿。
ご法座の帰り道にお寄りになったご法友と、大きな炉の火をかこみながら、「歎異抄」の第二条を涙ながらに語り合っていた光景は、温かく赤い炭の色とともに忘れ難い父の横顔でございました。
母もまたお給仕には誠を込め、勤行の姿もつつましく、「法の深山」「報恩講の歌」「真宗宗歌」などの讃仏歌をさわやかな声できかせてくれました。
お仏壇とは、および声に耳をすませて遠つみ祖先(みおや)の教えをいただき、お念仏をすすめて下さる親さまとの出会いの場でございましょうか。

お念仏申させていただく身となりましたことのお礼の念仏を申すところでございましょうか。
あさあさの母がつとめの正信偈
わが生くる日の一生(ひとよ)ひびかん
とお聞かせいただいたお歌が忘れられません。
北島豊美【北海道 北見市】
「お仏壇と私」(17)を紹介させていただきます。
『帰命無量寿如来 南無不可思議光・・・」と、父の調声で今日も家族そろってのおつとめが始まる。
今年の盂蘭盆会『うらぼんえ』。スーパーマーケットに行って、「お盆になるとお花も高くなるね。でも自分たちばかりごちそうを食べていたらもったいないわ」そう言って、仏さまの花を手に取る母。
輪灯などのおみがきをし、お餅や果物、お花をお供えする。
親戚の人たちも来て、お仏壇や先祖のお墓へお参り。食事の折には、亡くなった人を偲び、思い出話に花が咲いた。
新しく家が完成し、離れや住まいから母屋へ引っ越したころ、まだお仏壇は洗濯に預けてあった。
数日後、仏壇屋さんが届けて下さり、座敷の仏間に安置されると、「これでやっと家らしくなった」と喜ぶ両親だった。
また、こんな事もあった。私が娘を出産し、退院してきたとき、母は孫を抱いて車から降りると、すぐ仏壇の前に座り、「わが家の子ですよ」と仏さまに報告していた。
朝の忙しい時間、「あーまだお仏飯をお供えしていない。後にして、主人の弁当を詰めてしまおう」などと思ってしまう私。
座敷までの足取りの重いこと。でも、そんな私に今日も「必ずあなたを救う」と、やさしい眼差しで見つめて下さっているみ仏さま。
お仏壇は、わが家の中心。み仏さまは、私たち家族の支え。許され、励まされ、生かされて生きている。
両手を合わせ、素直に「阿弥陀如来さま、ありがとう」と、感謝の気持ちでいっぱいになる。
み仏の教えを、両親の言葉を、私自身が心して聴き、子に伝えていきたいと思う。
お仏壇の前に座ると「南無阿弥陀仏」のおよび声が身にしみる。
松井乃里子【岐阜県】

本当に生き生きとした文体で、感動的ですらあります。その時の光景が目に浮かんでくるようです。
やはり、宗教生活というようなものは、理屈ではなく、その渦の中に入り込んで、何かに触れることが大事な気がしました。
意味が分かろうが、分かるまいが、先ず、その宗教的環境の中に入り込んで、一緒に歩んでいるうちに、仏さまが生きる中心となって下さるように育てられるのではないでしょうか?
お仏壇の前に座ると、「南無阿弥陀仏」のお呼び声が身に沁みるように育てられるのではないでしょうか?
宗教的な「お育て」を頂くことは、今日、求められている大事なことだと思えてなりません。
最後に、朝枝思善師のご法話を味わわせていただきたいと思います。
『あんたはダイヤモンドだった 朝枝思善
先日ご門徒の「よとぎ」(お通夜)にお参りしたときのことであります。
主人を失った奥さんが、にこにこ顔で対応しているので、とてもびっくりしたのです。
まさか、ショックで頭が変になったのでは・・・と心配して話しかけてみました。
「どこが悪かったの」
「はい、直腸ガンで入院していました。」
「よく
「でもとてもわがままな所があって、金曜日の夕方には自宅に帰り、月曜日にまた病院に行く生活だったんです。」
「どうしてかと言うと」「それはご院家さんのお世話で新しい仏壇を購入したとき、
『仏壇は飾り物ではないお浄土の
と言われるのです。
このわがままはとてもすばらしいことなのですが、これだけではにこにこ顔の答えにはならないので、「もっと他になにかあったのでは」と聞いたのです。
すると実は一ヶ月前から寝たきりになり、家に帰ることは勿論出来ず、一日中
そして昨日私の手を握って「長いこと世話になったのー、あんたと一緒になってわしはほんまに幸せだった、ありがとう。と言いました。
そして

私は、まさかこの人がダイヤモンドなんて言ってくれるなんて考えてもみなかった。
私はうれしくてうれしくて私の方から「ありがとう」と言ったのです。
この言葉を聞いて、にこにこ顔の理由が分かったのです。
そばに居た家族、特に子供達が「お母さん何んでこのことを早く言わなかったの、みんなお父さんが死んで頭がおかくしなったのだと思った。そうなのそうなのお父さんがそんなことをお母さんに言ったの・・・。」
この会話は、肉親を失った通夜であり乍ら、何んとも明るい雰囲気の中での一ときでありました。
まさに如来さまを中心とした御同朋 御同行のご縁でした。
さて、私の人生にとって生死の問題、特に死の解決、いのちの行方が決定していない位
『あんたの

現代は
特に宗教に対する不信感が強いときです。こんな時代であればあるほど、私にとって浄土真宗とは何か、このことを鮮明にしなくてはなりません。
凡夫が仏にならせていただく教え、しかも弥陀同体の覚りをひらかせていただく救いこそ宗祖聖人によって開顕された浄土真宗です。
ダイヤモンドは光にあたってこそ輝きます。
私のいのちは浄土を建立せずにいられなかった阿弥陀さまの智慧と慈悲に
嬉しいことを沢山もってこそ人生の値打ちがあります。
このうれしさが笑顔となって表れるのです。
阿弥陀さまという
悲しい肉身の通夜でありながら、浄土真宗のみ教えに生きるすばらしい姿を味わうことが出来ました。』
(朝枝 思善師 ご法話『見真』より)
ここに「仏壇は浄土の出店だから、朝夕必ず仏参し、阿弥陀さまにご挨拶をし、時にはお寺に参って聴聞する」
という言葉がございます。
「仏壇は浄土の出店」ということはどういう意味でしょうか?
お浄土から、わざわざお仏壇の姿になって、日々苦悩して生きる悲しい性の私のために、「仏さまと共に生きておくれ。」と願いはたらいていて下さるご本願に目覚めてこそ、 「真実の親に出会えたうれしさ」というものではないでしょうか。

ある先徳は「如来様は 生死海を活動舞台として 常に光明を放って 衆生を喚(よ)んでいて下さる 生死は如来の御いのちである」と言われました。
仏さまの「必ず救う」の真実の親の働き・ご本願に出会う場所がお仏壇と言っていいのではないでしょうか。
今を生きる真実の依りどころとなり、不退転の歩みをさせて下さる大きな大きなバックボーンを頂く場所がお仏壇なのかも知れません。
我々の先祖が残して下さった、宝を決して無駄にしないようにしたいものだと自戒する次第です。称名
南無阿弥陀仏
『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』
☆☆法語☆☆
| さまざまの悲しみや、苦しみは |
| 人間の生活にとってさけることの |
| 出来ないものである。 |
| 生きているということは、悩まねば |
| ならぬということであり、問題は |
| この悩みにいかに答えるかという |
| ことにある。人間の精神は、生活の |
| 破綻に直面して、もがき、苦しみ、 |
| それが深い自覚にまで高められて形 |
| づくられてゆくものであり、 |
| この悩みを超える道は、苦悩を |
| 背負って立つ以外に見出される |
| ものではない。仏法は、苦悩の中 |
| から、みずから立ち上がろうとする |
| 人間の上に、法として聞こえてくる |
| ものであり、救いは、悩みの中に |
| すでにその光を放っているものであ |
| る。 |
ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌
最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。
「今ここでの救い」

