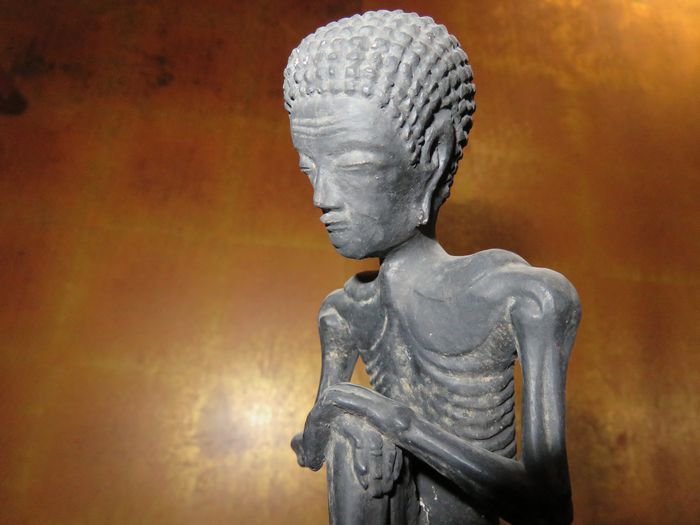
|
「我も |
住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。
今月は「我も
旧年中は色々とお世話になりまして、有難うございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。 称名
昨年は色々なことがございました。皆さんも同じではないかと思います。
色々な苦難に会われながら頑張っておられる方々を見聞きすると、私も頑張らなければならないと思わされます。
苦しみは、一人一人違い、人それぞれであります。
宗教というものは、今・生きている私に対して、救いの働きを受け止めることがなければ宗教の意味はないと教えられました。
浄土真宗では「はからい」ということを厳しく否定するところがございます。
仏様のお心は私のようなものに分かるわけはない、ただ仰せのままに聞き入れ、受け止めるしかないのに、自分の力で、仏様の心を理解していこうとすることが「はからい」であります。
浄土真宗の教えの根本は「本願」であると教えられています。
「本願」とは、何としてでも衆生を救いたいと願う仏・菩薩の慈しみの心・大慈悲心からおこされるもので、誓願ともいう。
衆生を救済するために誓った誓願を「本願」という。
「本願」は、「本(もと)からの願い」という意味である。
阿弥陀仏という仏陀に成った法蔵菩薩の四十八願は、「大無量寿経」に説かれている。
『大無量寿経』に、阿弥陀如来のお心が説かれている。
「全てのものを自分の国に迎え入れて、もれなく仏陀にならしめたい。もしそれが出来ないようであるないなら、私は仏陀と呼ばれる資格がない」と誓われた。
そして、その本願を実現して、法蔵菩薩は、自らを阿弥陀仏と名告るのである。

「阿弥陀」という言葉は、「無量」とか「無限」を意味する。
それは、全てのもののいのちが、あらゆる限定を超えて、共に在る、同じ一つのいのちであることを表している。
私たちは、何よりも「自分が可愛い」という、自分中心の「自我の心」を、どうにしても離れることが出来ない。
その結果、誰とも共に生きることができず、孤独で不安定な人生を生きることになってしまっている。
そんな「落ちこぼれの私」を悲しんで、阿弥陀仏は、そのいのちの真実に目覚めさせようと、本願を建てたのである。
「こころ貧しき私 故」の「本願」である。
私たちが、あらゆる限定を超えて、共に在る、同じ一つのいのちに目覚めることができた時、「さまざまな違いを超えて、共に生きる」という、歩みが始まるのである。
ある方が仏法の席で先生に質問をした。「親鸞聖人の偉いところはどういうところですか?」と。
その時、先生は、「今までで一番良い質問だ。」と大変褒められたという。
「親鸞聖人の偉いところは、落ちこぼれの私たちのために、本願を説かれたところである。」と答えられた。
本願に会われたことを喜ばれた高僧に源信和尚がおられる。「横川法語」を書かれた高僧である。
「横川法語」について、山本仏骨師が解説しておられる。
「現代人のための親鸞」雄渾社 から、抜粋して、紹介させていただきます。

『「横川法語(よかわほうご)」は源信僧都(げんしんそうず)の残されたご法語であり、「横川」というのは、叡山の横川谷のことで、僧都(そうず)は一生ここの恵心院というお堂ですごされたから、 横川の僧都(そうず)とも、また恵心僧都とも申し上げるのであります。
わたくしは心から、この僧都をお慕い申し上げておるのであるが、その聖跡である横川の恵心院へ、いくたびとなく詣でて、師の芳躅を景慕しました。
源信僧都は、朱雀天皇天慶五年(942)に生まれられ、後一条天皇寛仁元年六月十日(1017)に76歳でおかくれなさっているから、いまから約一千年前、親鸞聖人より約二百年ほど前のおかたです。
僧都の郷里は、中将姫の伝説で有名な、大和の国当麻(たいま)であって、幼少のころ父をうしない、賢明な母の手に養育されたが、九つのとき叡山にのぼり、叡山中興の師と仰がれた 良源上人のもとに学ばれた。
のちに横川で、恵心院流の学派を開拓された功績は、日本天台のうえからいっても大きなものであるが、僧都は性来 名利をいとうて、みずから権勢の巷に出ず、静かにお念仏をよろこんで、経論に親しみ、 著述に専念されたのであります。
親鸞聖人は真宗を伝承した七高僧のなか、第六番目の祖とさだめ、日本における真宗の初めの師とあおがれたのであります。
わたくしが、僧都をお慕い申し上げてやまない理由は二つあって、一つには僧都は深く名利をいとうて、ひたすらお聖教を書くことに専念されたということであり、二つにはあれだけひろい学問と高い お徳をつみながら、少しもそのような顔をせず、自分は妄念のかたまり、極重悪人であるとへりくだって、だまって仏様のまえに頭をさげ、お念仏をよろこんでいかれた態度です。
僧都は「名利」という二字を紙にかいて、それを壁にはって、いつもおがんでおられたということで、人がそのわけをたずねると、「これはお母さんの教訓だ」と答えられたそうであります。
源信僧都自身はつねに わが身をかえりみて「横川法語」には妄念のかたまり ということを徹底していわれ「往生要集」には「極重悪人」と告白されている。
学問をすればするほど、修行をつめばつむほど、わが身はえらくなった というよりは、むしろ自己のおろかさに気づかれたのである。
僧都ほどの学問とお徳には、われわれはとても足もとにもよりつくことができない。
だから、おまえたちと自分とは格式がちがうのだ とつきはなされても、われわれには一言の抗弁もできないはずである。

それに僧都は、みじんもそのような顔をせず、われわれと同じ立場にへりくだって、だまって仏様の前に頭をさげ、仏様のくださったお念仏のお乳をいただいていかれたのである。
ここにわたくしは かぎりない僧都のおくゆかしさを慕わずにはおれないのであります。
まことに人は、うぬぼれと自我心の強いものであって、物を知らぬとはいいたくない。
人にまけまい、ひけをとるまいという競争心のとれないものである。
ここに日夜きゅうくつな悶えがつきまとうて、苦しまねばならないのであり、あなどりと、ひがみのあらそいがたえないのである。
そうした対立、きしめきのなかには憩いもなければ救いもない。
結局おろかなくせに賢こぶっていこうということが、煩悶苦悩のたえないゆえんでありましょう。
その点僧都は、さらりとうぬぼれをすてて、仏様のお慈悲のなかに憩い、真実の知恵をみがいていかれたのであります。
人間は競争心をすてたら発展がないという人がある。一応はそうも考えられよう。
しかし、このような対立のなかから生まれた発展が、果たして自分も他人も真に幸福になれるような、ほんとうの発展でありうるだろうか。
他人をつきおとしてでも、自分さええらくなったら という競争のうちには、つねに呪いと涙がひそんで、やがては崩壊していくものであることに気づかねばならない。
人間には、たしかに他の動物には見られない、いいところがあるに違いない。しかし反面人間には、どの動物よりも恐ろしいものを持っている。
虎や狼は人におそいかかって噛みつくが、結局は一対一で、一人を噛み殺すだけである。
しかし人間はいっぺんに、何千万という人を殺すような核兵器を造りだしておるではないか。
また人間はどの動物よりもみにくい心をひそめている。
犬や猫は食べさせてさえおけば、おとなしくなついて、いうとおりになる。

しかし人間は人の裏をかいて、悪だくみをしたり、あらぬことをくわだてていきます。
そこに、なまじ知恵をもった人間こそ、もっとも始末の悪いものだといわねばならない。
しかしこうした自分の自性も照らされねばわからない。うぬぼれと自我心に、盲目的になっていくおのがすがたは、仏の叡智に照らされてこそはじめてわかることで、はてしない暗がりに 沈んでいくおのれのあさましさは、まことの光に遇うてこそ、はじめて救われることができるのであります。
人は迷いの多いもので、一つの物事を行うにしても、あれかこれかと迷い、悩まぬものがどこにあろうか。
また人は誤まちの多いものであって、しずかに自分の通ってきた過去をふりかえってみると、すべてが誤まちの連続であったと、恥じられるであろう。
そのときは真剣に、まちがいないと思い、最善の努力をつくしたつもりでも、あとからふりかえってみれば、あれも誤まりであった、これも誤まりであったと思うことばかりである。
まことに妄念の凡夫であり、極重悪人であったというほかはありません。
さればこそ源信僧都は、かかる人のさがをかえりみて、仏様の前にひれ伏していかれたので、このように叡智に照らされてこそ、はじめて人はまことの光に浮かびあがるのであり、あたたかい慈悲に いだきとられてこそ、すべての人を許す気持ちにもなって、なにごとも耐えしのんでいくことができるのであります。
かくて僧都は、つねに仏様を「極大慈悲の母」と仰いでお念仏をよろこばれたのであります。
その源信僧都がお書きになった「横川法語」は、短い一枚の法語にすぎないが、ここに僧都の一代の蘊蓄がこめられ、限りない味が汲みとられるのであります。
それでは、このご法語には何がいわれているのかというと、一言でいえば、僧都の「およろこび」を告白されたので、それは「よろこぶべし」「よろこぶべし」というおことばを 折りかさねて述べられておることでうかがわれます。

そして、その「およろこび」を述べられる三段あって、まず第一に、それ一切衆生、三悪道をのがれて、人間に生まるること、大きなるよろこびなり。
身はいやしくとも畜生におとらんや、家はまづしくとも餓鬼にはまさるべし、心におもふ事かなはずとも、地獄の苦しみにくらぶべからず、世のすみうきはいとうたよりなり。
人かづならぬ身のいやしきは、菩提をねがうしるべなり。
このゆへに人間に生まるる事をよろこぶべし。
といわれたのは「人間に生まれたというよろこび」であり、第二に、
信心あさけれども、本願ふかきがゆへに、たのめばかならず往生す。
念仏ものうけれども、唱ふればさだめて来迎にあづかる。
功徳莫大なり。このゆへに本願にあふ事をよろこぶべし。
といわれたのは「本願に遇えたというよろこび」であり、第三に、
また妄念はもとより凡夫の地体なり。
妄念の外に別の心もなきなり。
臨終のときまでは、一向に妄念の凡夫にてあるべきぞとこころへて念仏すれば、
来迎にあづかりて蓮台に乗るときこそ、妄念をひるがへして、
さとりの心とはなれ、妄念のうちより申しいだしたる念仏は、
濁りにしまぬ蓮のごとくにして、決定往生うたがひあるべからず。
妄念をいとはずして 信心のあさきをなげき、こころを深くして常に名号をとなふべし。
といわれたのは「お念仏をいただいたというよろこび」であります。
このように、三段におよろこびを述べられているが、しかし三つ別々のものがあるのではなくて、つまり一つの「およろこび」に他なりません。
すなわち人間に生まれたというよろこびは、本願に遇えたというよろこびであり、本願に遇えたというよろこびは、お念仏をいただいたというよろこびであり、 お念仏をいただいたというよろこびが、はじめにかえって人間に生まれたというよろこびになるのであります。
このように内容をわけていえば、三つになるが、それはまるい一つの円周のようなもので、一つにつらぬいていたよろこびの告白であるとうかがわれます。』
【「現代人のための親鸞」山本仏骨 雄渾社 より】

この落ちこぼれの私をお救い下さるよろこび、本願に遇うことができたよろこび、全て、私たちに教えを伝えて下さった方々のお陰であります。
「恩徳讃」に「如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし 師主知識の恩徳も ほねをくだきても 謝すべし」
とありますが、この朝から晩まで、妄念の 私をして 欲を超えた聖なる世界へ向かう流れに入れられていることを何となく感じ、 仏 法 僧 三宝の御恩を念じ、手を合わし念仏申します。
本年も、ご教導よろしくお願い申し上げます。 称名
『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』
☆☆法語☆☆
| *角【つの】あるは機【き】なり |
| 合掌するは法なり |
| 法よく機を摂【せっ】す |
| 柔軟【にゅうなん】なり三業 |
| 火車【かしゃ】の因滅【めつ】す |
| 甘露心に恢【あきた】る |
| 未【いま】だ終焉【しゅうえん】に |
| 到【いた】らざるして |
| 華台【けだい】迎接【げいしょう】す |
| *心も邪見 身も邪慳【じゃけん】 |
| 角【つの】を生やすが これが |
| わたくし |
| あさましや あさましや |
| なむあみだぶつ なむあみだぶつ。 |
| あさましいの 邪見の角が |
| 生えた まんまで |
| 親にとられて |
| なむあみだぶつ なむあみだぶつ |
| 浅原才市 |
ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌
最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。
「今ここでの救い」

