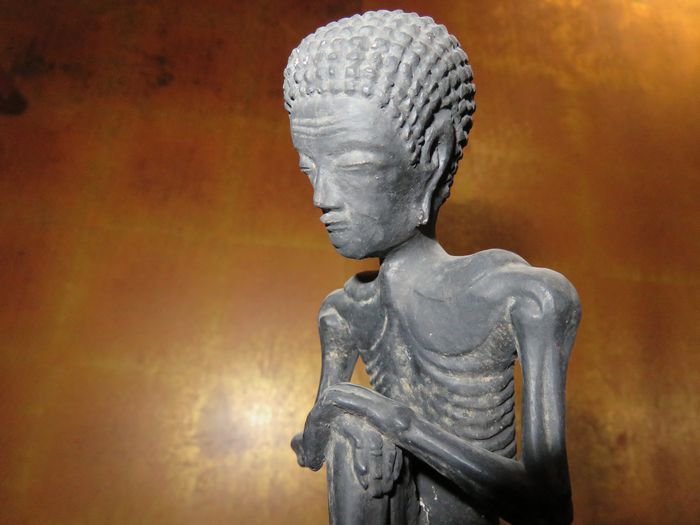
|
「このまま |
住職法話をお読み頂きまして、有難うございます。
今月は「このまま
「求道六十年 歎異抄を生きて 生きがいへの出会い 木村無相」光雲社 という本に次のように書いてありました。
『じかづけに
波がヒタヒタ うちよせる かわいた岸に うちよせる かわいた砂に うちよせる
み名がヒタヒタ うちよせる かわいた心に うちよせる かわいた胸に うちよせる
ナムアミダブツ ナムアミダブツ
昭和十九年頃、長崎県の雲仙嶽の麓の麓の小浜という温泉町から、一里程行った漁村にて、ありがたい法談をかさねていた頃、その帰り道、
村一番というありがたい老婆、その方は八十四、五でしたが大変元気で、まだ一人前に働いているのでしたが、海岸端をつれだち歩いているうち、ひとり言のように、
「まこと(マコト)、ヒタヒタとなあ、ヒタヒタとなあ、」
と、感に堪えたように言ってはお念仏しているので、
「お婆さん、それいったいなんやね、ヒタヒタとなあ、は」
と、しつこくたずねると、お婆さんは、やっと念仏をやめて、
「それでもお前なあ、こうして浪うちぎわを歩いていると、沖の方から静かに、この岸にうちよせて来て、このかわいた砂浜を、ヒタヒタと、うるおすではないか」
そう言って一息ついて、
「なあお前、わたしの煩悩でかわききったこの心、この胸に、お念仏さまが、ヒタヒタと打ちよせてくれては、このかわいた心を、このかわいた胸を、ヒタヒタとうるおしてくれるではないか」
と、言って、それからは、お婆さんは涙でほほをぬらしながら、しかし顔をかがやかせて、またお念仏しつつ、せっせと小浜の町へ波打ちぎわを歩いてゆくのでした。
その時のことが、ひどく若い私の心にしみこんでか、それから三十年も経った後、フッと出来た詩が、この念仏詩「じかづけに」なのでした。
降るわ降るわ 煩悩無尽(ぼんのうむじん)と 雪が降る 降るわ降るわ 大悲無倦(だいひむけん)と 雪が降る
私の詩と信仰(NHKラジオ「宗教の時間」(昭和五十二年)に放送された太子園老人ホームでのお話です。)
子供の時から、世の中の濁った中で転々として育ったので、とてもませて、すれていました。
そして親の生活を批判し、世の中の奴は皆薄情だというふうに、悪いところばかり眼をつけて まあ、えらい悪いことですが、陰ではお父さん・お母さんとは言わずに、ジジイ・ババアと 言っていたのです。
「たのみもせんのに、こんな世の中に生んでくれやがって、自殺するなら、先ずジジイとババアを殺してから、そのあと、薄情な世の中の奴らを、五、六人は殺して死ななければ 引き合わん」と、十五、六の頃には、表向きはおとなしい子と言われながら、肚ではそんなことを考えていた私でした。
実にひどい性格でして そのくせそういう自分は、さほどに悪いとは思っていなかったのです。
そりゃまあ、まるきり良いとも思っていませんでしたが、それは実に微かなもので。

ところが、忘れもしない満二十歳の十一月三十日の夜のこと、ある事が縁になって、今まで外ばかりに向いていて、両親や世間をあげつらうことばかりをしていた眼が、どうしたことか、 一斉にパッと自分の内側に向けられてしまって それは決して、自分でそうしようとしてそうなったのではなくて、パッとそうなった。
パッとそうなったら、さあ大変 人を憎んだり、恨んだり、嘘ついたり、ゴマかしたり、腹立てたり、そういう色々な煩悩が、心の奥のどこからか次々と現れて来て、それぞれの働きをしては、 次々と消えて行く。
その心の奥は暗くて、どれだけ深いかわからない 「これはまあ、なんというヒドイ俺の根性か」と全く驚いて、「この悪い煩悩の心を断ち切って、悟りが開きたい」と、そう思い立ったのです。
その頃、すでに一家は離散、縁があってその後、鹿児島の小学校の代用教員になった無相さんは、次第に大きく重くなって来た此の問題のために先生を辞めて、求道一筋の旅に出かけます。
満洲各地を放浪し、昭和四年には先輩に誘われてフィリピンの開拓地に渡り、さまざまな宗教の門を叩きます。
昭和八年、自分の問題を解く鍵は仏教の中にありそうだと気付いて、満二十九歳で日本に帰ると四国遍路をはじめます。
そこで耳にした愛媛県のある寺で、三年間真言の教えを学びますが、自分の教えを受けるには自分の力が足りないことを自覚して、今度は徳島県の真宗のお寺で四年間他力の教えを学びます。
しかし、そこでも自分の煩悩を除く糸口は見いだすことが出来ず、寺を出る決心をします。
お寺を出てからの昭和十五年一年間は全くスランプでした。
お寺を出る時に私は「お前はとても駄目だ。なんぼ聞いても読んでも頭だけで、胸にはちょっとも受けつけない。仏法は落第だから、求道とか聞法は止めにして、自分の身についている煩悩だけで 生きることにして、街へ出てほかの人と同じように働きなさい」と自分自身に言い聞かせてお寺をお暇して、それから、つてを求めて静岡市のある個人会社の住込みの事務員として働いたのですが、その当時も 続いて送ってくださっていた松原致遠先生の個人雑誌の『無碍道』も、帯封も取らずに押し入れの中に放り込んで、娯楽雑誌を読んだり、映画に行ったりの生活でした。
そうした昭和十五年の十月のある日、会社が休みで映画を観に行っての帰りに、静岡駅の前を通りかかった時、全く思いもかけずフッと、「生死出離ということは、南無阿弥陀仏と、 今ここに既に成就されているではないか!」という声が閃いたのです。
私は愕然として思わず立ち止まってしまったのでした。寺を出てからの一年間は、仏法についてのことはぜんぜん考えたことが無かったのです。意識的には。
しかし、心の底ではやっぱりそのことが問題であったのか、問題にしていて下さったお方があって、眼を離さないでいて下さったからか、「生死出離ということは、南無阿弥陀仏と、 今ここに既に成就されているではないか」と、フッと来るものがあって、「ああ、これはこうしては居られん。南無阿弥陀仏について、真剣に聞かせて貰わねばいかん」と思い立ったのでした。
再び法を聞く決心をした無相さんが、今度教えを受けることになったのが、三重県の松原致遠さんのお寺でした。
松原致遠先生には、昭和十六年・十七年とマル二年お膝元でお育てをいただいたのですが、先生はお若い時はかなり御気性のはげしいお方だったとのことですが、それだけに、その業の深い 深い中から現れて下さるお念仏は、まことに身に沁みるものがあり、それはそれは常念仏の尊いお方でした。
先生は、毎月講演や御法話の旅へ出られて、御在寺は月のうち僅か一週間ほどでしたが、私は先生の御在寺中は、どこでも着いて行くのでした。お便所でも、それは、いつも御法のことしか念頭にない お方でしたから、着いてさえ行けば「木村さんこの弥陀の名号称えつつの つつ はなあ」というふうに、その時々のお味わいを、独り言のように言ってお聞かせ下さるのでした。
それはそれは、お念仏に聞き入るような御態度での常念仏のお方でして、御自坊の本堂でのお説教の時も、「ここはお念仏の道場ですから、世間話は家ですることにして、ここではお念仏を申して下さいよ」 とおっしゃるので、お詣りの人達もお説教とお説教の間には、ナンマンダブ・ナンマンダブと、静かにお念仏を申しながら、次のお説教を待つのでした。

私も真言時代から、お念仏だけは口についていましたから、お念仏はついつい申すのですが、煩悩とお念仏との関係がついていないので、ただ声に申すだけで、お念仏の味わいはわからないのでした。
お念仏申すと、ちょっと信者らしくカッコウはいいんですが、自分でわかりますものねえ。
お念仏と自分が溶け合っていないということが、 道がついておらんのです。
先生も見るに見かねたんでしょうねえ。奥さんも女中さんも居ないある日のこと、おかずはしてくれていますから、先生と二人で昼食を済まして、先生はナンマンダ・ナンマンダと御自分の
書斎に行ってしまわれ、私は洗った茶碗・皿を茶の間の水屋に向かって座って、ナンマンダ・ナンマンダと片づけていましたら、書斎の方から先生がバタバタッと走るようにやって来られて、 私の後ろに立たれたかと思うと、驚くような劇しい大きな声で、「名号とは!?」とおっしゃった。
そこで私が思わず反射的に大声で、「功徳!」とお答え申したら、「いや、智慧じゃ!」と、叩きつけるように言い捨てて、先生はまた書斎の方に、ナンマンダ・ナンマンダと行ってしまわれたのです。
そこで私、ひどく考えさされましてねえ。「俺がお念仏を
それから後もずっと、そのことについて考えさされたんですが、先生の処にお世話になっている間は、「いや、智慧じゃ!」が、わからなかったのです。
聖人も『唯信鈔文意』に、「この智慧の名号を濁悪の衆生に与えたまえるなり」とおっしゃって下さっているのに。
南無阿弥陀仏の名号が、煩悩に苦しむ我が身をお助け下さるという味わいが、三十路の中ばを越えても、無相さんはどうしても受けとれず、再び若い頃学んだ真言の道を求めて、今度は高野山へ登ります。
高野山の大学で勤めながら法を聞き行もしますが、ここでも迷いが消えず、行の途中で山を降りてしまいます。
「そうやって聞き歩くのもよいが
能信院師のおんさとし

「
「
これは、
「鯛ならよいが、鰯だったらどうしましょう」身だけいただけと言うが、私の会った人が鰯だったら」というわけで、それはまことに
表向きだけは殊勝げに「どうか、お聞かせ下さい」と言うんですが。
ちょうど、今朝拝読した聖人の『唯信鈔文意』の中に「心口各異」というお言葉がありましたが、口で言うことと、肚の中で思っていることとがまるで違う。
「
といいますが、その
しかもそれを性懲りもなく何十年となく繰りかえして。

二度三度、真言と浄土の間を迷い歩いているうちに、五十の坂を越した無相さんが、最後に落ち着いた処は、いずれの行もおよび難い人間ほど助けてやりたいという、阿弥陀如来の 本願力に救われている世界でした。
自分の
自分のあがきを捨てた処に、広がっていた世界でした。
ひらくもの
わがこころ 貝のごとくに ふと閉じぬ この哀しみを ひらくもの ただねんぶつの ほかはなく ただねんぶつの ほかはなく
この
貝なども蓋を外から開けようとするほど、蓋は開かない。
ところが、お念仏さまはそうでない。外から蓋をこじ開けようとするのではなしに、内から、この
お念仏さまは、南無阿弥陀仏さまは。
それで結局、私はいつの場合もナニカにつけて、ナンマンダブ・ナンマンダブで「阿呆の一つ覚え」ですが、それも私が覚えているわけでなくて、お念仏さまが忘れておくれぬ。
南無阿弥陀仏さまが忘れておくれぬ。
それこそ「寝ても覚めてもへだてなく」私の煩悩の内らで働いていて下さって、この業人の口を開いて外に、ナンマンダブツ・ナンマンダブツと現れて下される。
結局はいつも南無阿弥陀仏さまが、お念仏さまより外ないというところに、立ち帰らせて下さるのです。
ひらかれると
自分が ひらかれると 自分が ひらかれると 自分が ひらかれると 天地いっぱい
ひとたび「天地いっぱい」という世界を知っても、人間の心は生きもの、煩悩は次ぎから次ぎに湧き出て来ます。

そのままで
信者になったら おしまいだ 信者になれぬ そのままで ナンマンダブツ ナンマンダブツ
「信者になれぬそのままで、ナンマンダブツ ナンマンダブツ」ところがコイツが、信者になりとうて、なりとうて、かなわんのです。
ちょっとチヤホヤされると、すぐ信者顔して喜んでいる。煩悩が喜ぶんですねえ。
けれども、信者にかかっている御本願ではないんでしょう。
信者になれない、どうしても信者になることの出来ない私にかかっている大悲の御本願なんでしょうから、信者になってしまっては、もう聞こえない。
それなのに、ちょっとチヤホヤされると、すぐに嬉しがって信者になってしまって、自分は聞こうとしない。
聞かせ屋になってしまっては、自分にはもう聞こえませんね。
聖人の『唯信鈔文意』の中に、「釈迦如来、よろずの善の中より、名号をえらびとりて、五濁悪時・悪世界・悪衆生・邪見・無信の者に与えたまえるなりと知るべし」とありますが、私はこの 「無信の者」というお言葉に、いきなり足を払われたように、驚かされたのでした。
私がもともと「無信の者」であるのなら、私がどれだけ自分の力で信者になろうとしても、なれる筈がない。
もともと信者の芽が出るような種が無い、根がないのですから。
「信じて助かろう」にも、「信ぜよ」言われても、「信心正因だ」言われても、どれだけ言われても、ところが、さあ、そういわれると、すぐに私は自分の胸を見る。
そして有りもせん信心を探す。
そして、無いということも、よくわからんのですねえ。わからんからこそ、なんとか此の凡夫持ち合わせの心を働かせて、それで信じて助かろうとするんです。
何十年となくそうして来たんですが、こんな者がどれだけバタバタしても、肝心の信の根がまるっきり無い「無信の者」とあっては、なんとしても真実信心になれよう筈はなく、私としては 「信」ということには、全くお手上げの外は無いのです。
そういう私に残された唯一の道は、如来さまが、「よろずの善の中より選びとりて」お与え下されるという南無阿弥陀仏の御名号を、ただただお与えのまんまに、ナムアミダブツ・ナムアミダブツと、 「悪衆生・邪見・無信の者」のまんまに、「信者になれぬ、そのままで」おいただきするより外に私の道は無いのです。

歓喜というも
わたしの苦労ばなし ナニになる 如来さんの御苦労 聞く一つ 「聞其名号 信心歓喜」
如来さんの御苦労に わしゃ歓喜 歓喜というも ナムアミダブツ 歓喜というも ナムアミダブツ
とかく人さんにお会いしますと、私は煩悩で自分の苦労ばなしをし勝ちです。
また、向こうさんもそれをお尋ねになる。
ところが、こんな者が一生だろうが、万生だろうが、どれだけ苦労したって、お助けの一段になると、こんな者の苦労や体験では助からんのです。
それで私はこう思うんです。
体験・体験言っても、「歎異抄」にも、「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて往生をば遂ぐるなり」とあって、「無相の体験に助けられまいらせて往生をば遂ぐるなり」とは無いです。
それで、「わたしの苦労話、ナニになる」で、聞くべきものはひとえに「如来の御苦労」であると言うほかありません。
私としても、真言時代ならともかくも、聖人のみ教えを聞かせていただく今としては、自分の苦労や体験めいたものに、功を持たせるわけにはいきません。
それで「如来さんの御苦労に、わしゃ歓喜」と言っても、私の歓喜なんて言うものは、ほんの一時的なものですから、「歓喜というもナムアミダブツ・歓喜というもナムアミダブツ」で、 如来さまの御苦労をナムアミダブツといただくまんまが、私における歓喜であって、お念仏の外に、ヤレ歓喜だ、ヤレ苦労だ、ヤレ体験だと、腰かけるようなものは、ナニ一つ無いのです。
私は「われ今ここに、いのち生くる」というこん日ただ今の「生」に、「いのち」に、驚いているのですが、また、「今日ひと日、ひと日のいのち」という「今の無常」にも、此の齢になって驚いているのです。』
【「求道六十年 歎異抄を生きて 生きがいへの出会い 木村無相」光雲社 より抜粋】
長い引用となりました。木村無相さんの言葉には、不思議な吸引力があり、グングン引き込まれていくのを感じます。
木村無相さんほど、求道されると、自分の苦労や体験を言いたくなるのが、人情というものではないかと思うのですが、木村無相さんは、「如来さまの御苦労話」をされます。
宗教には、体験談というものが大きなものになっているような気がします。それは、やはり、教えをただ聞くだけでなく、自分の身に付いていなければ、力にならないからです。
自分の実感とか、体験というものは、素晴らしいものだと言えますでしょうし、良いものでもあります。
私も何十年も教えを聞いてきた中で、私なりの実感・宗教体験というものがありました。
しかし、それが揺り動かせられる出来事がありました。
それは、先月、91歳の母が、体調が悪いので、かかりつけの医師に診てもらいました。検査して点滴して頂いたのですが、検査の結果があまり良くはありませんでした。
それで、大きな病院を紹介していただいて、入院することになりました。
その病院には、母は近年は何回か入院して、病院の雰囲気や病室にも慣れてきていました。
入院して、「二週間くらいの入院でしょうか。」と主治医からのお話でした。
ところが、次の日に、病院から呼び出しがあり、母の容態について説明がありました。率直に言えば、厳しいことを言われた、ということですね。
母の子供や孫が、飛んで来てくれました。交代で添い寝をしました。
私も3回 添い寝をしました。
平成5年に、62歳で、亡くなった父は、七つの病院に入院して、12年の闘病生活の末亡くなりましたが、父の見舞いには行きましたが、添い寝をしたことは、ほとんどありませんでした。
母の病状が良くない中での添い寝は大変辛いものでした。
添い寝をしても、母は中々私を寝させてくれませんでした。結局、朝の6時頃に、やっと寝てくれました。
病状の良くない母に添い寝して、病室で、深夜、91歳の母もいつかは死ぬ時が来る。
それと同時に、わたし自身にも死が必ずやってくる。
死を乗り越えて行かなければならないんだ!。そんなことが、強く思われてなりませんでした。
私も、三十代から、今日まで、約30年、私なりに一生懸命、仏法を聴聞してきました。
しかし、病室で、母にも、わたしにも同じように迫ってくる死というものを思った時、とても乗り越えられそうにありませんでした。
「今まで一生懸命聞いてきた仏法は一体何だったのか?」と自問自答せずにはおれませんでした。
宗教において、自分の実感とか、体験というものは大事なものだと思いますし、良いものだとも思います。
しかし、「自分の実感とか、体験というものは、変わっていくものでもあるんだなあ。」
そういうことを考えずにはおれませんでした。
夜中、真っ暗な中で、病室で、母に、添い寝して、寄り添うことは、大変心細く、辛いものがありますが、太陽が昇り、昼頃になり、町全体が明るくなると、不思議にこちらの心も、自然と楽になってきました。
「太陽の力って、すごいなあ!」と、しみじみ感じさせられました。
阿弥陀さまのことを、親鸞聖人は「真実明」と言われています。「明」という字が使われていますが、お浄土とは、「明るい明るい世界」で、今、仏さまは、明るい世界から見ていて下さるのでしょう。
木村無相さんの言葉には、死の前で、無力感に打ちのめされている私に、そんな壁を乗り越えて行く、その道が示されているように感じました。
母は、主治医の治療や、病院のスタッフの24時間のサポート体制のおかげで、一か月の入院生活の後、治療の効果があって、不思議と退院することが出来ました。
今日で、退院して、約二週間になります。よく退院できたなあ!と思い、不思議でなりません。
退院しても、色々大変なことはありますが、帰宅することが出来た事は大きなことですね。
近所に、私の恩師でもある、もうお亡くなりになられましたが、有難いお婆さんが住んでおられました。
「お寺の鐘が聞こえるのが有難い。」と言われるような近所に住んでおられた方でした。
浄土真宗の学びに、一生精進された方でした。
その方が、私に、入院した時の話を聞かして下さったことを思い出します。
そのお婆さんが、病院に入院された時、医師が看護婦に、そのおばあさんのことを話しているのが、おばあさんに、聞こえたそうです。
「今晩が山だな。」と医師が言っているのが聞こえたというのですね。
それを聞いて、ショックを受けたわけです。その時、お婆さんは、「今まで仏法を浴びるほど聞いてきたけれど、自分が助かることを聞いてこなかった。」と感じられたそうです。
そんなことを思いながら、どれくらいの時間かわからないけれど、病院のベッドの上で、うなだれていました。
すると、「そういうお前だから、救わずにおれないんだよ。」という阿弥陀さまの声なき声が聞こえてきた、と言われました。
そのお婆さんは、何とか持ち直し無事退院されたのではありましたが。
私も母に添い寝しながら、「今まで仏法を一生懸命聞いてきたのに、私を支える力にならない気がする。」と感じて、大いなる無力感を感じていました。
しかし、そういう私に仏さまの「お前を救わずにおれないんだ。」という限りない働きを感じさせられました。
親鸞聖人の御和讃に次のような御和讃がございます。
「願力無窮(がんりきむぐう)にましませば 罪業深重(ざいごうじんじゅう)もおもからず
仏智無辺(ぶっちむへん)にましませば 散乱放逸(さんらんほういつ)もすてられず」『正像末和讃』
願力とは阿弥陀如来が、この私を必ず救うと願いはたらいて下さっておられる無限のおはたらきのことです。
それが無窮、極まりが無いので、どれほど深く重い罪であろうとも救われないことはないと言われるのです。
仏智は、阿弥陀さまの智慧のはたらきは、無辺であるから、つまり、阿弥陀さまの智慧のはたらきが広大無辺で、広く行き渡る。
その働きは、この私に到り届いて、救わずにおれないと無限の働きをして下さっている。
どんな人であろうと分け隔てなく平等に救って下さるお慈悲の活動であります。
散乱放逸とは、「散り乱れた心の勝手気ままな行い」という意味だそうですが、散り乱れた心で自分の好き勝手に生活しているこの私でさえも 阿弥陀如来は、嫌うことなく、区別することなく必ず救って下さるのだということであります。
無明長夜の灯炬(とうこ)なり 智眼(ちげん)くらしとかなしむな
生死大海の船筏(せんばつ)なり 罪障(ざいしょう)おもしとなげかざれ 『正像末和讃』
阿弥陀如来の本願は、煩悩によって迷う、何一つ確かなものなどわからない凡夫である私を照らす灯火であるから、智慧の眼が暗いと悲しむことはない。
阿弥陀如来の本願は、生死の大海での救いの大きな船であり筏であるから、障りがあり、悪業が深いと嘆くことはない。
このご和讃は、娑婆世界を無明の闇の中で苦しみながら生きる私に、励ましのお言葉を送って下さっているように響きます。
何一つ確かなものがない真っ暗闇の中で、弥陀の本願に導かれて、今、おさめ取って捨てないと働き、帰るべき親里である浄土の確かさと有難さを頂けるのは、今、わたしに呼びかけるお念仏さまのおかげ でありました。
宗教の世界で、宗教体験は良い事であり、素晴らしいことではありますが、厳しい状況の中で、変わっていくことがあることを、母に添い寝している病院の病室の中で、つよく思わされました。
浄土真宗は、「聞くに始まり、聞くに終わる」と申します。
「み教えを聞く」ということ、親鸞聖人の書かれた浄土真宗の根本聖典であります「教行信証」も「教」つまり「教え」から始まっているように、「み教えを聞く」という原点を忘れたくない 、と思っています。称名
『ご清聴頂きまして、有り難うございました。 称名』
☆☆法語☆☆
| *自然 |
| 自然 ああ 今 その |
| イキづかいが 聞こえる |
| *道がある |
| 道がある 道がある |
| たった一つの 道がある |
| 「極重悪人 唯称仏」 |
| *阿弥陀堂の前で ご本山にて |
| 「マンマンちゃん |
| アンするんですよ」 |
| わかいおかあさんが |
| おしえている |
| ああ あわせた コドモの |
| 小さなお手よ 【木村無相】 |
ようこそ、お聴聞下さいました。有難うございました。合掌
最後に、本願寺が作成した「拝読 浄土真宗のみ教え」の一節を味わわせて頂き終わらせて頂きます。有難うございました。
「今ここでの救い」

